住民のために一刻も早く
西日本豪雨災害

▲写真は小田川の氾濫で地域の大半が冠水被害を受けた岡山県倉敷市・真備地区。高梁市・岡山市も大きな被害をうけています
「平成30年7月豪雨(以下、西日本豪雨)」では、西日本を中心に大きな被害が出ました。被災自治体では職員が被災者支援と復旧活動に奮闘しています。全国各地から自治労連の仲間がボランティアとして駆けつけ、自治労連本部も総務省への緊急要請など対応を行っています。(下記に詳細)
ストップ 長時間過密労働
大幅賃上げで生活改善を
暑さに負けず2018夏季闘争勝利へ 7・25中央行動

▲全国から集まった自治労連の仲間を代表して決意表明する高知自治労連・吉田佳弘書記長
全労連などが主催した7月25日の中央行動は、すべての労働者の賃上げと最低賃金の大幅引き上げ(関連6面)を求め、各省庁前での要求行動と、日比谷野音での7・25中央総決起集会、銀座デモを展開。全国から2000人を超える仲間が参加しました。また自治労連は独自行動の総務省要求行動、「つなぐアクション」決起集会を実施しました。
主張 核兵器廃絶と平和憲法
憲法を遵守する自治体公務公共労働者をめざして
今年も、平和を考える夏が巡ってきました。
1945年8月6日、9日に広島・長崎へ原爆が投下され、その年の終わりまでに、広島では約14万人、長崎では約7万人の命が奪われました。そして、8月15日に終戦を迎え、1947年5月3日に「もう戦争はごめん」と、二度と戦争をしないことを決めた平和憲法を手にしました。
各地の最賃闘争
格差拡大許さず抜本的引き上げを
全国最賃引き上げ目安は「26円」
民間労働者だけでなく、公務公共サービス職場で働く労働者の賃金底上げや、公務員高卒初任給にも大きく影響する最低賃金の引き上げ額の全国目安を決める中央最低賃金審議会が7月24日に行われ、目安額は全国平均26円となりました。
原発立地・周辺自治体を訪問し懇談(茨城県)
再稼働 「事前了解」自治体拡大協定締結
自治労連原発ゼロ・再生可能エネルギー政策検討委員会

▲那珂市での懇談。向い側の右端が海野市長
2018年11月に営業運転開始から40年の運転期限を迎える東海第二原発(茨城県東海村)は、期限延長の審査が予定されています。2018年3月29日には原発の再稼働等について「同意についての事前了解」を茨城県と立地自治体だけでなく、隣接市と一部隣々接市にも拡大する新安全協定が、国内で初めて周辺5市を含め、6市村により締結されました。
すすむ非正規公共評(44)
議会へ理解を求め処遇改善となる条例を要請
広島自治労連 広島市嘱託労組連絡会

▲広島市嘱託労組連絡会を代表して市議会各会派に要請する留守家庭労組の平松ゆう子委員長(右)
広島市嘱託労組連絡会は、6月18日に広島市議会各会派を訪問し、「広島市で働く臨時・非常勤職員の処遇改善についての要請」と「公務職場の嘱託職員の実態を訴えるレポート2017」を提出しました。
シリーズ14 いちから学ぶ仕事と権利
「一括法」廃止の声をあげよう 実効性ある労働時間規制を
「働き方改革」でどうなる職場と社会
第196回通常国会で強行採決され成立した「働き方改革」一括法で、最終的に何が決まったのでしょうか。
みんなで学んで元気に
第38回 自治体にはたらく女性の全国交流集会 in 岩手 7月7~8日

▲400年の歴史をもつ和太鼓。地域の若者による雄大な演奏に参加者は感動に包まれました
第38回自治体にはたらく女性の全国交流集会が岩手・盛岡市内で行われました。地域住民のいのちとくらしを守る自治体労働者の役割を確認しあい、参加者も現地実行委員も元気が出た集会となりました。
18年国民平和大行進
列島各地からヒロシマ、ナガサキへ
今月の連載・シリーズ

8冊目
富田 武 著
中央公論新社 2016年12月発行 新書判・262ページ 定価:860円+税

第30録
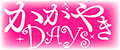
〔49〕
千葉県職労 行川(なめかわ) 貴浩(たかひろ)さん

Collection49

第80品
広島市職労 加藤 朋子さん
びっクリーミーなサッパリパスタ