すべての子どもを笑顔に
全国から3500人 11・3保育大集会

▲銀座パレードで「公的保育制度を守ろう」とアピールする高知の仲間
「子ども・子育て支援新制度」(「新制度」)は2015年4月から実施されましたが、保育料が3倍に値上げされた保護者が札幌、大阪などで不服申し立てを行うなど、さまざまな混乱を引き起こしています。こうしたなか、「子どもたちによりよい保育を!11・3大集会」が日比谷野外音楽堂で開催され、保育者、保護者、保育関係者ら3500人が全国から集まりました。
待機児童の解消は認可保育所の新設、公立保育所の拡充で
自治労連独自行動

▲有楽町駅前で署名活動にとりくむ
大集会前の午前には、自治労連として、200人が有楽町駅周辺で署名や宣伝活動を行い、45分間で100筆の署名を集めました。
11・4国会議員要請行動
保育士不足の解消、処遇改善を
全国から300人が参加

▲要請行動の後、議員会館前での決起集会
集会翌日の11月4日、政府・国会議員要請行動に300人が集まり、午前中の情勢学習では藤井伸生氏(京都華頂大学教授)が講演しました。
職場要求の実現めざし2015秋季年末闘争
愛知・新城市職労、福岡・北九州市職労

▲地区協の仲間も交渉に駆けつけ(愛知・新城市職労)
安倍政権はNO 11・12中央行動に3000人
地域間格差拡大許さず賃上げで生活改善
戦争法 派遣法改悪 TPP 原発再稼働 辺野古新基地建設強行

▲全国から集まった公務の仲間が総務省前でシュプレヒコール
全労連・国民春闘共闘は秋季年末闘争勝利に向け11・12中央行動を3000人が参加して展開。自治労連も全国から150人超が参加しました。
看護職員不足の解消、勤務条件の改善を
「看護職員の労働実態アンケート結果」にもとづき厚生労働省要請・記者会見を実施

▲厚労省(右)に病院職場の改善を要請
自治労連は2014年11月から今年1月にかけて4年ぶりに実施した「看護職員の労働実態アンケート」の最終報告書にもとづき、自治体病院職場の過酷な労働実態や看護職員の声を届けるために11月13日、厚生労働省要請と記者会見を行いました。
いのちと地域を守る 自治体病院の役割を学ぶ
第17回 自治体病院全国集会

▲分科会で熱心な討論が行われました
集会は岩手・盛岡市内で11月14~15日に開催し、全国から医療関係職場で働く仲間142人が参加しました。
主張 公的サービスの「産業化」は許さない
公務公共サービス拡充にむけ共同を広げよう
2015年7~9月期のGDP実質は年率換算で△0.8%と4~6月期に続き2期連続のマイナスとなりました。中国経済の減速で世界同時株安が進行、日経平均株価も下落に転じ、日本経済は回復がままならない状況です。
7年連続の県内全自治体訪問
自治体訪問で処遇改善すすむ
自治労連島根県事務所

▲7年連続の全自治体訪問で信頼関係も(写真は松江市)
島根県事務所では、今年は「憲法と地方自治をいかした、地域再生のとりくみ」をテーマに、県内全自治体(県、8市11町村)を訪問しました。7年連続の全自治体訪問です。この時国会では、憲法違反の「安全保障法制」議論の真最中であり、「憲法をめぐるメッセージ」の要請もしました。
「数が力」をモットーに要求実現に向け支部結成
高知公務公共一般 香美市保育園支部

▲組合加入を訴え続けてきたことが支部結成へ
高知自治労連では、今年2月の自治体非正規・公共関係労働者全国集会が高知で開催されたのを契機に、非正規職員の組織化のとりくみについて本格的に議論されはじめました。
すすむ非正規公共評(12)
労働条件改善とよりよい学童保育をめざす
神奈川・横浜市従 学童保育指導員支部

▲若い指導員が働け続ける職場にするため団結ガンバロウ
横浜市従学童保育指導員支部は1991年に結成しました。長く働き続けられる賃金労働条件の改善と、よりよい学童保育の実現にむけとりくんでいます。
11月8日 憲法をいかす地域の再生を考えるシンポジウム
幅広い「地域再生」の共同すすめ 憲法がいきる社会へ
「地方創生」は地域・住民に何をもたらすか

▲特別報告の後に行われたパネルディスカッション
全労連主催「憲法をいかす地域の再生を考えるシンポジウム」が11月8日、東京・全国教育文化会館において開催され労働組合や民主団体などから96人が参加しました。
第56回 地方自治研究 愛媛県集会
中小企業こそ日本経済の主役
「中小企業振興基本条例」の制定で明るく元気な地域を創ろう

▲地域を活性化するために熱心に講演を聴く参加者
愛媛県本部主催、愛媛県自治体問題研究所共催の「第56回地方自治研究愛媛県集会」を11月8日に愛媛県伊予市で開催し、112人が参加しました。午前中は、①まちづくり・地域活性化・委託民営化、②医療介護・社会保障、③現業、④いのちの水、⑤保育、⑥青年講座の6つの分科会で行われました。
「2000万人署名」に全力
戦争法を廃止しろ
毎月19日は抗議行動の日

▲11月19日夕方、国会正門前に9000人が集まる。首都圏から参加した自治労連の仲間
戦争法案が強行採決された9月「19日」を忘れないとりくみとして、総がかり実行委員会(「戦争をさせない1000人委員会」「解釈で憲法9条を壊すな!実行委員会」「戦争する国づくりストップ!憲法を守り・いかす共同センター」)主催で、11月19日に国会正門前集会に9000人が結集しました。
関東・東北豪雨被災地へボランティア派遣
本格復旧はこれから
岩手 大船渡市職

▲左から高橋さん、橋本さん、多田さん、村上さんとボランティアで仲良くなった外国の方
関東・東北豪雨で大規模な水害に襲われた茨城県常総市を支援しようと、大船渡市職と岩手自治労連では、ボランティア派遣を行いました。ボランティアに参加したのは、高橋大介さん(市街地整備課)、橋本邦彦さん(会計課)、多田宗さん(税務課)、村上智哉さん(港湾経済課)の4人です。
今月の連載・シリーズ

第19景
愛知県名古屋市・ピースあいち
世代超えた市民の交流の場
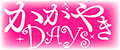
〔19〕

Collection19

第50品
愛媛・松山市職労 戸田 克江さん
おいしすぎてやめれんこん♡